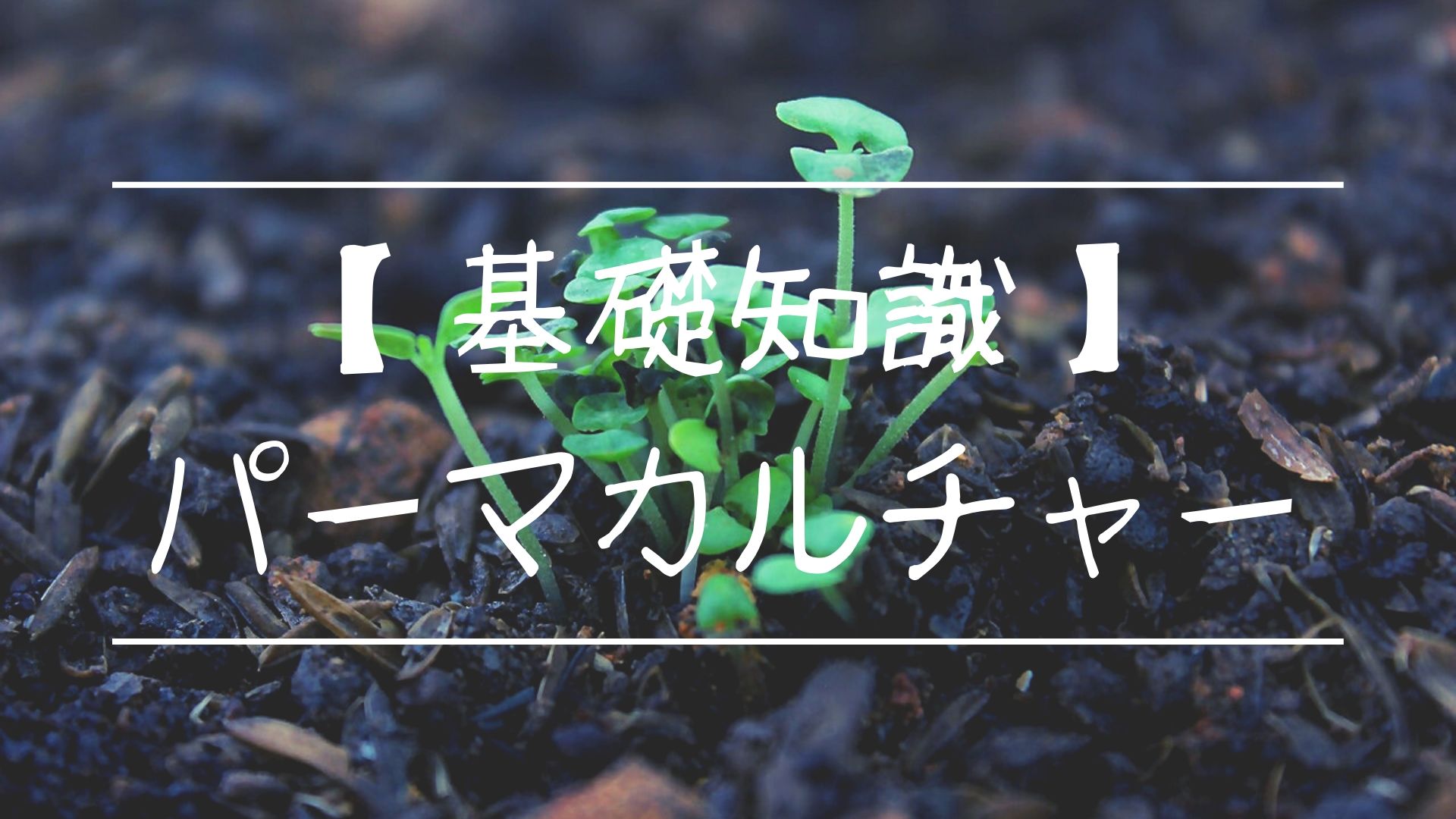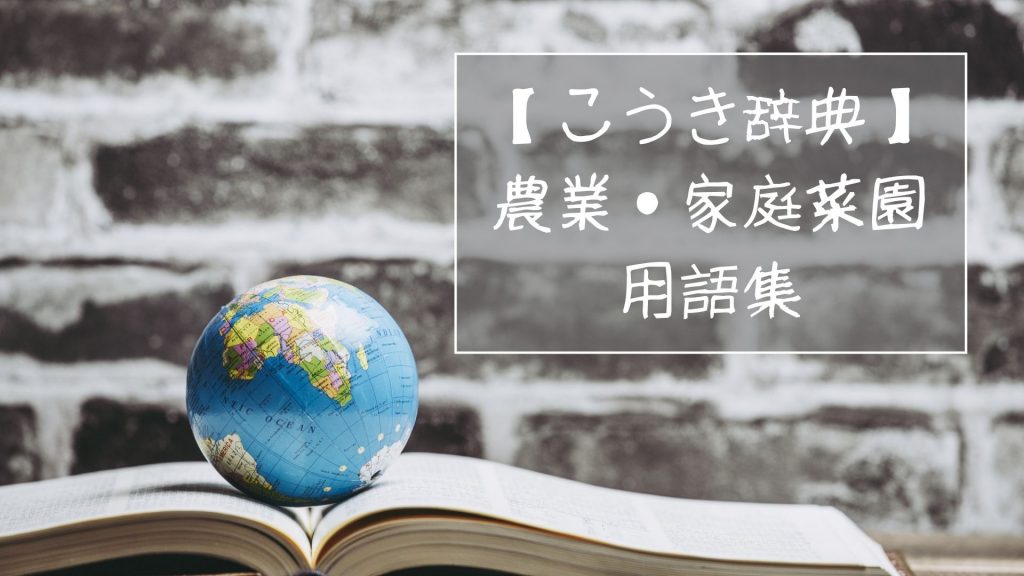
農業・家庭菜園を取り組む際に出てくる用語を解説する用語集です。
分からない単語があれば随時使用してください。参考になれば幸いです。
※随時追加していきます。
「あ」行
育苗(いくびょう)
苗を育てること
種まきから苗立ちの間集中管理することにより、苗の質を上げる。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
【選日】この日に種をまくと、1粒の籾が万倍にもなる稲穂になるという意味。
転じて、この日に何か始めると、何倍にも膨らむ日。
種まき日和。吉日
「二十四節気」と「日の十二支」から定められる。
【こんな方におすすめの記事】➤「一粒万倍日」とは何か知りたい人➤「一粒万倍日」の決め方を知りたい人 ➤「一粒万倍日」に行うと良いことが知りたい人【目次】① 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは?② 2020年の一粒万倍日③ 一粒万倍日に行うと良いこと④ 一粒万倍日に行うと良くないこと⑤ まとめ
畝(うね)
種をまいたり、作物を植え付けたりするため、畑の土を盛り上げたところ。
盛り上げることにより排水性がよくなる。
お礼肥(おれいごえ)
収穫が終わった後に行う施肥。お礼(感謝)の意味込めて行う施肥
「か」行
株間(かぶま)
作物の株の中心から隣の作物の株の中心までの距離
基肥(きひ)
種まき・苗の移植をする前に、土へ施しておく肥料のこと
元肥(もとごえ)、原肥(げんぴ)ともいう
種まき・苗の移植から収穫まで長い期間効果が必要で、有機質肥料や緩効性化成肥料、遅効性肥料がよく利用される
嫌光性種子(けんこうせいしゅし)
光を嫌う種子。光によって発芽が抑制されるという性質を持つ。
暗発芽種子ともいう。
覆土は厚めにする。覆土厚の目安は種直径の2~3倍程度
例:大根、カボチャ、トマト、ピーマン、玉ねぎなど
原肥(げんぴ)
種まき・苗の移植をする前に、土へ施しておく肥料のこと
元肥(もとごえ)、基肥(きひ)ともいう
種まき・苗の移植から収穫まで長い期間効果が必要で、有機質肥料や緩効性化成肥料、遅効性肥料がよく利用される
好光性種子(こうこうせいしゅし)
光を好む種子。発芽に光を必要とする種子
光発芽種子、明発芽種子ともいう。
覆土は必要最小限にする。
例:ニンジン、小松菜、レタス、白菜、シソなど
硬実種子(こうじつしゅし)
種子の皮に透水性が無いため、水分を吸収することができず、自然状態では休眠状態にある種子
そのままでは発芽率が悪いため、種子ごとに適切な硬実処理を行う。
例:ほうれんそう、オクラ、かぼちゃ、ゴーヤ、すいかなど
硬実処理(こうじつしょり)
硬実種子に対して発芽を促進する処理
水につけたり、皮の一部に傷をつけたりする
五季(ごき)
春夏秋冬に土用を加えたもの
五節句(ごせっく)
中国の暦法で定められた季節の変わり目のこと
人日の節句、上巳の節句、端午の節句、七夕の節句、重陽の節句
コンパニオンプランツ
近傍に栽培することで互いの成長によい影響を与え共栄しあう2種以上の植物の組み合わせのこと。
共栄作物 、共存作物ともいう。
例:トマト×バジル、ぶどう×クローバー、いちじく×ミントなど
「さ」行
雑節(ざっせつ)
五節句・二十四節気以外で、季節の移り変わりの目安となる日
例:節分、八十八夜、土用など”
直まき(じかまき)
畑や花壇に直接まくこと(移植はしない)
【こんな方におすすめの記事】➤「種まき」の種類を知りたい人 ➤「種まき」のコツを知りたい人【目次】① 種まきの種類 ② 種をまく深さ(覆土について)③ 種まき~発芽のステップ ④ まとめ
四季(しき)
春夏秋冬4つの季節のこと
仕立て(したて)
どうやって作物を育てるか?その方法論
仕立てをすることにより、管理が容易になり、質の良い作物が多くとれるようになる。
整枝+誘引を合わせて仕立てという。
仕立て=整枝として扱うこともある。
条(じょう)
植物を植え付けた列のこと
1列なら1条植え、2列なら2条植えという。
条間(じょうかん)
条と条の間のこと
条まき(すじまき)
種まき方法のひとつ。溝を設けて、溝に沿って列状に種をまく方法
【こんな方におすすめの記事】➤「種まき」の種類を知りたい人 ➤「種まき」のコツを知りたい人【目次】① 種まきの種類 ② 種をまく深さ(覆土について)③ 種まき~発芽のステップ ④ まとめ
整枝(せいし)
主枝、側枝などを明確にし、不要な枝・果実をとること
整枝により管理をしやすくし、質のよい果実を多く作れる。
整枝=仕立てとして扱うこともある。
施肥(せひ)
土壌に肥料を施すこと
選日(せんじつ)
六曜、十二直、七曜、二十八宿、九星、暦注下段に含まれないものの総称。お日和、お日柄のこと。撰日・雑注ともいう
例:1粒万倍日、犯土、天一天上など
「た」行
単粒構造(たんりゅうこうぞう)
砂や粘土など細かい粒子だけで作られた単一的な構造の土壌
粒子同士の結合がなく排水性が高すぎ、肥料もち、水もちが悪い。濡れるとドロドロ、乾燥するとカチカチになる。
野菜作りには向かない土壌
対義語:団粒構造(だんりゅうこうぞう)
団粒構造(だんりゅうこうぞう)
土壌粒子が団子状になり集合体を形成している構造の土壌
粒子同士が結合しており、排水性・保水性・通気性に優れる。
いわゆる良い土。野菜作りに向いている土壌
対義語:単粒構造(たんりゅうこうぞう)”
点まき(てんまき)
種まき方法のひとつ。一定の間隔で点(くぼみ)を作り、種をまく方法
【こんな方におすすめの記事】➤「種まき」の種類を知りたい人 ➤「種まき」のコツを知りたい人【目次】① 種まきの種類 ② 種をまく深さ(覆土について)③ 種まき~発芽のステップ ④ まとめ
トウ立ち
塔立ちとも書く。花芽が作られた後、花茎が伸びだすこと。
植物自身が大きくなる栄養成長から種子を残すための生殖成長に転換する転換点。
トマトやきゅうりなどの果菜類は収穫のためにトウ立ちが必要
小松菜やほうれん草などの葉物類、大根やにんじんなどの根菜類はトウ立ちすると食味が落ちたり、栄養が少なくなったりする。
床まき(とこまき)
ポットやセルトレーに種をまくこと。ある程度育ててから畑や花壇に移植する手法
【こんな方におすすめの記事】➤「種まき」の種類を知りたい人 ➤「種まき」のコツを知りたい人【目次】① 種まきの種類 ② 種をまく深さ(覆土について)③ 種まき~発芽のステップ ④ まとめ
土用(どよう)
【雑節】「土旺用事」の略
土の気が旺(さかん)に働く時期。年4回約72日ある。
【こんな方におすすめの記事】➤「土用」とはそもそも何か知りたい人 ➤「土用」はいつを指すのか知りたい人 ➤「土用の丑の日」とは何か知りたい人【目次】①そもそも土用とは?②土用とはいつなのか?(2020年を参考に)③土用にやりたいこと、控えた方がいいこと④おまけ:土用の丑の日とは?⑤まとめ
「な」行
苗立ち(なえだち)
種が発芽し、双葉から本葉が伸び始め、自立した状態・移植ができる状態になること
苗半作(なえはんさく)
苗で半分作る。苗作りの出来が作物の出来の半分を決める。
よい苗が作れれば、それだけ作物の出来もよくなるという意味。”
二十四節季(にじゅうしせっき)
1年を24の節目で分けたもの。1節は約15日
例:夏至、冬至、春分、秋分など
「は」行
パーマカルチャー
1974年にオーストラリアの生物学者ビル・モリソンと教え子のデビット・ホルムグレンが構築した人間にとっての恒久的持続可能な環境を作り出すためのデザイン体系のこと。
パーマカルチャーは、下記を組み合わせた造語
パーマネント(permanent永久の)+
アグリカルチャ-(agriculture農業)orカルチャー(culture文化)
※日本語訳は「農的暮らしの永久デザイン」
【こんな方におすすめの記事】➤そもそも「パーマカルチャー」とは何か知りたい人➤「パーマカルチャー」の考え方を知りたい人➤「パーマカルチャー」について知識を深めたい人【目次】①そもそもパーマカルチャーとは?②パーマカルチャーの基本的な考え方 ③【具体例】スパイラルガーデン、アースオーブン ④パーマカルチャーがわかる本 ⑤パーマカルチャーに取り組んでいるグループ・団体などのご紹介
こうきが選ぶパーマカルチャーを学ぶのに最適な本を解説【おすすめの本】①パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン②地球のくらしの絵本(1) 自然に学ぶくらしのデザイン③パーマカルチャー事始め
ばらまき
種まき方法のひとつ。土の上に種をそのままばらまく方法
【こんな方におすすめの記事】➤「種まき」の種類を知りたい人 ➤「種まき」のコツを知りたい人【目次】① 種まきの種類 ② 種をまく深さ(覆土について)③ 種まき~発芽のステップ ④ まとめ
日の十二支(ひのじゅうにと)
十二支に合わせて日をカウントする考え方
「ま」行
芽かき(めかき)
わき芽を摘み取ること。
わき芽が小さいうちに芽かきした方が苗への負担が小さい
元肥(もとごえ)
種まき・苗の移植をする前に、土へ施しておく肥料のこと
基肥(きひ)、原肥(げんぴ)ともいう
種まき・苗の移植から収穫まで長い期間効果が必要で、有機質肥料や緩効性化成肥料、遅効性肥料がよく利用される
「や」行
誘引(ゆういん)
茎や枝、つるを支柱に固定し、伸ばしたい方向へ導くこと
仕立てを行う際には、必須の技術
作物の形を整え、管理が容易になる。実の重さや風などで苗が倒れないようにする。などの効果がある。
「ら」行
リレー栽培(りれーさいばい)
前作の野菜が後作の野菜の環境作りをすることにより、病原菌の減少や生長促進などを図る栽培
例:タマネギ→カボチャ、ダイコン→キャベツなど”
輪作(りんさく)
同じ場所において、複数の作物でローテーションを組み、順番に栽培していく方法
連作障害を予防することができる。
例:(1年目)じゃがいも→(2年目)大豆・枝豆→(3年目)かぼちゃ→(4年目)じゃがいも→・・・”
連作(れんさく)
同じ畑で、同じ作物を続けて栽培すること
連作を続けることにより発生する障害を連作障害と言う。
同じ作物とは、全く同じ品種の作物だけではなくて、野菜の植物学的な分類で「同じ科に属する野菜」のことを意味する
例:トマト→なす(2つとも同じナス科なので連作)
「わ」行
わき芽(わきめ)
茎の先端以外の芽。葉や茎の付け根にできることが多い。
作物の生長状況を見ながら適宜芽かきを行う。
「A~Z」
K(かりうむ)
カリウムの略。植物3要素の1つ
光合成や炭水化物の移動蓄積に関与。
【主な効果】
・硝酸の吸収、たんぱく質合成に働く。
・開花結実の促進
・根や茎を強くする
N(ちっそ)
窒素の略。植物3要素の1つ
たんぱく質・アミノ酸・葉緑素・酵素の構成成分
【主な効果】
・根の発育・茎葉成長の促進
・養分の吸収同化の促進
P(りん)
リンの略。リン酸を指すこともある。植物3要素の1つ
呼吸作用や体内エネルギー伝達に重要な働き・
【主な効果】
・植物の生長、分けつ、根の伸長、開花、結実を促進
用語集は随時更新していきます。
こういった用語も欲しいなど要望があればこちらよりご連絡ください。
以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。